質問コーナー Q&A

出産を控えていたり、育児で働き方が変わったりしている従業員へのサポート制度をご存じですか?
産前産後の収入保障「出産手当金」や、将来の年金額が下がらない「養育期間標準報酬月額特例」など、知らないと損する制度を分かりやすく解説します。
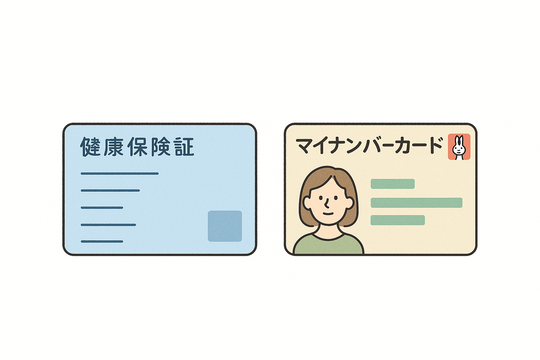
マイナ保険証への切り替えが進む中、従来の健康保険証がいつまで使えるのか、またマイナンバーカードを持っていない人はどうすればよいのか。
知っておきたいポイントを整理します。
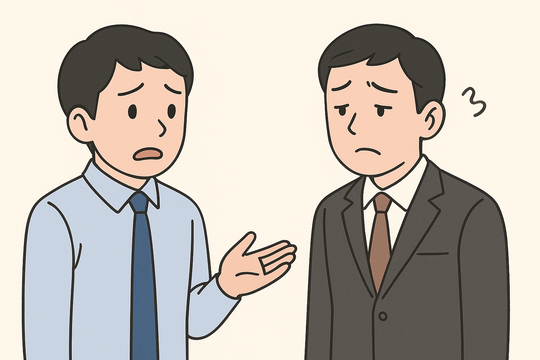
従業員の家族がインフルエンザにかかった際、感染防止のため会社が休業を命じることがあります。本人に症状がなく「勤務したい」と申し出ても、会社は応じる義務はありませんが、ただし会社都合の休業となるため、休業手当の支払いが必要となります。

副業やダブルワークなど色々な働き方が広がる今、有休付与や労災認定の取り扱いなどに悩まれる経営者は多くおられます。
本記事では押さえておくべきポイントを解説します。

有期契約の終了、いわゆる「雇止め」は、適切な手続きと説明が求められます。とくに契約更新を重ねた労働者や長期勤務者に対しては、事前予告や理由の書面交付が法律で義務付けられていることをを説明いたします。

有期契約を繰り返し更新していると、雇止めが無効と判断されたり、無期転換権が発生して解雇が無効とされるリスクがあります。適切な対応をしないと、法的トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

社会保険料の決定方法には年に一度、全被保険者に対して行われる「定時決定」以外に、報酬に大きな変更があった際に行われる「随時決定」があります。その随時改定について説明させていただきます。
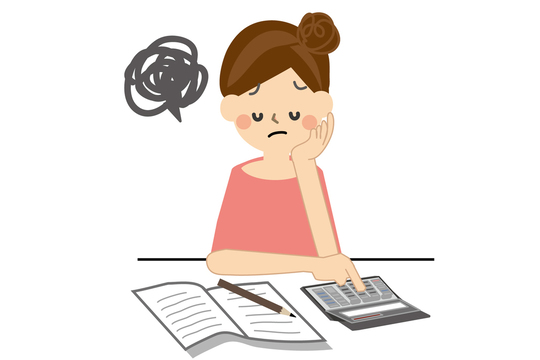
労働基準法上、給与の日割り計算の方法については明確に規定されていません。そのため、会社の規定に従って計算する必要があります。給与の日割り計算として、多く用いられる計算方法について説明させていただきます。

雇用保険に加入している従業員から離職票の交付を希望された場合、会社は必ず離職票の発行手続きを行う必要があります。
また、2025年1月からは離職票について新しい運用が開始されていますので、離職票の発行について解説いたします。

一緒に働く仲間を探すための採用面接時には、お互いにミスマッチが起きないように、色々なことを聞きたい反面、聞いてはいけないこともあります。
今回はメンタルヘルスに関する質問について回答いたしました。

従業員の体調管理はとても大切です。しかし、本人が自主的に受診していなかったり、治療を受けていない場合、会社として見過ごすわけにはいきません。
産業医への面談や、医療機関の受診を促す、命じることについて解説しました。

定年延長をする企業は年々増えています。制度を新しくする際には、考えなければならないことも増えます。
今回は定年延長に伴って退職金制度を変更する際のご相談を受けました。退職金制度を変更することは可能ですが、労働者の不利益とならないよう慎重に対応する必要があります。

コロナ渦移行、テレワークを導入されている企業も多くあります。
その、テレワーク中に従業員がけがをした場合、労災保険はどうなるのかについて回答します。

従業員に支給するパソコン等の貸与物が退職後に速やかに返却されなかった事例の相談を受けました。
法律等や労使協定で定められている賃金から控除できる項目について回答します。

うつ病発症はトラブルに発展する恐れがあります。
「会社のせい=労災」となるかどうかを判断するための要件や、従業員の主張内容とうつ病発症の因果関係の検証などについて、回答させていただきました。

労働基準法では、タイムカードの記録時間よりも労働時間の実態を優先しています。実態と記録が異なる場合は、正確な労働時間の管理が求められます。
今回は、始業時間前よりも早く出勤している時間が労働時間として認められるのかの相談について回答します。

特別休暇の条件や付与日数については、法律上の義務はなく、企業が自主的に決定するものです。多くの企業では、特別休暇を福利厚生の一環として設けています。
今回は、血縁関係のない親族の忌引きについて、対応を迷われた企業様からの相談に回答します。
