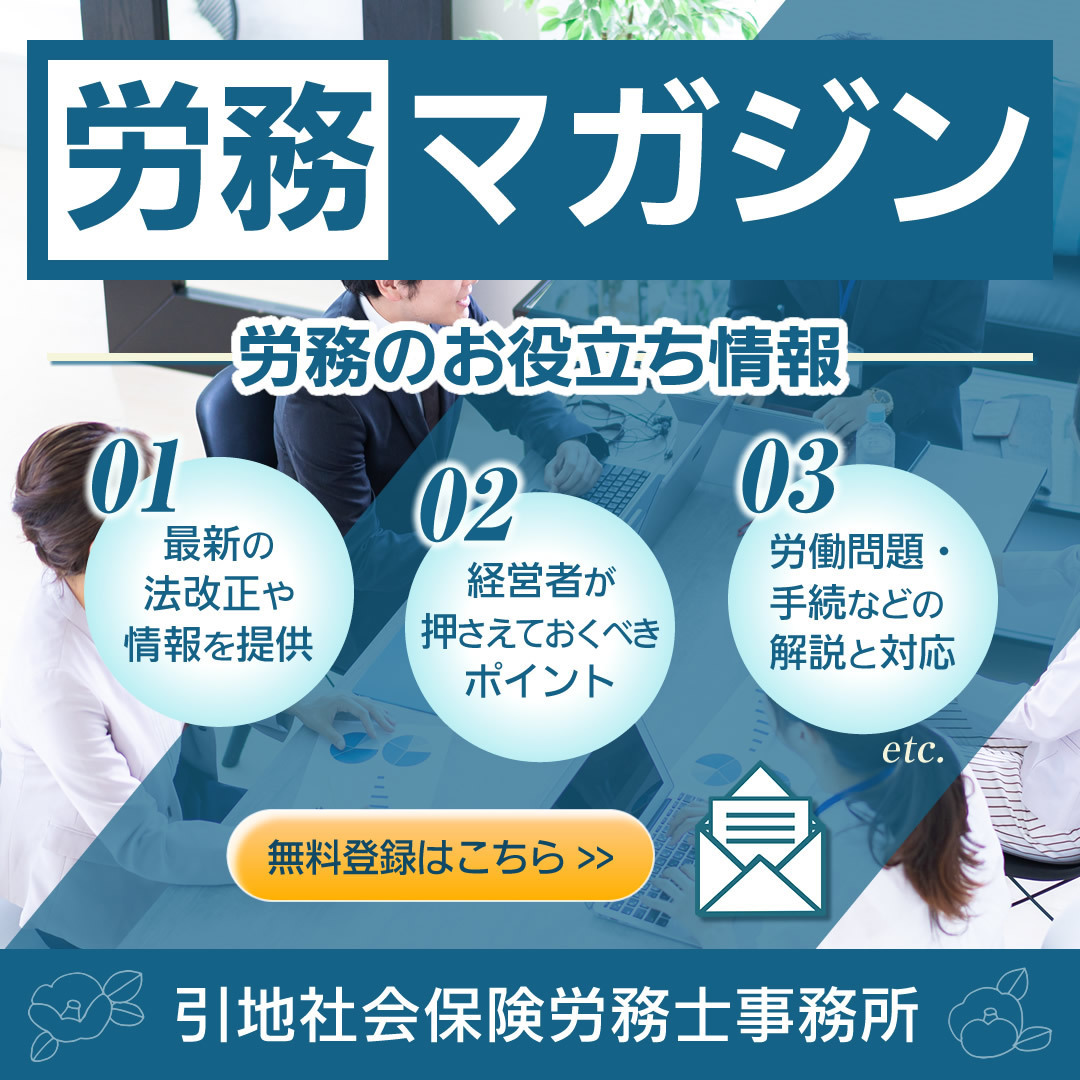お役立ち情報
2023年12月1日から、アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されました。
2022年4月1日に実施された道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車(マイカーや業務用の移動車、会社の荷物運搬車など)を運用する企業は、運転手の飲酒状態を確認するアルコールテストの義務が生じました。
当初、2022年4月からアルコール検知器の使用が必須となる予定でしたが、需要の急増による供給不足が発生し、実施は2022年10月に延期されました。その後、半導体の不足やコロナ禍による物流の問題で、さらに延期が発生しました。そして2023年12月1日、アルコール検知器の使用がついに義務付けられます。
この記事では、アルコール検知器を用いたアルコールチェックと企業の対応について詳しく説明します。
アルコールチェックの義務化の背景
2021年6月、千葉県八街市で発生した悲惨な事故があります。
飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み、5名が死傷しました。当時、緑ナンバー車(バスやタクシーなど)はアルコールチェックが義務付けられていましたが、白ナンバー車にはそのような義務はありませんでした。この事故のトラックも白ナンバーでした。これを受け、飲酒運転の撲滅に向けた警察の取り組みが強化され、白ナンバー車を使用する企業に対してもアルコールチェックが義務付けられました。
2022年4月からは、業務の前後に安全運転管理者によるアルコールチェックが必要となり、「視覚的確認」と「確認記録の保持」が実施されることになりました。
2023年12月からは、これまでの視覚的確認に加え、以下2点が安全運転管理者の業務に追加されます。
・アルコール検知器を使って運転者の飲酒状態を確認すること。
・アルコール検知器を常に稼働状態に保つこと。
アルコールチェック義務化の対象
義務化の対象は、安全運転管理者を選任する必要がある事業所です。選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行われます。
| 乗車定員が11人以上の自動車 | 1台以上 |
| その他の自動車 | 5台以上 |
安全運転管理者には、選任後15日以内の警察署への届出と、年1回の講習が義務付けられています。また、自動車を20台以上使用する場合は、副安全運転管理者の選任も必要です。
(参考:警察庁HP「安全運転管理者制度」)
検知器を用いたアルコールチェックの対応内容
1.アルコール検知器の導入
使用するアルコール検知器には、次の機能が必要です
・呼気中のアルコールを検出する機能
・警告音、警告灯、または数値でアルコールの有無や濃度を表示する機能
特定のメーカーや機種の指定はなく、持ち運びが可能なもの、データを集約し記録するもの、クラウドで管理できるものなど、各種機能を備えた検知器が市販されています。企業に最適な機種を選ぶことを推奨します。
2.検知器の常時稼働
2023年12月からは、アルコール検知器が常時正常に機能し、故障がない状態常に稼働状態に保つことが求められます。検知器の適切な使用と管理、定期的な故障チェックが必要です。
3.アルコールチェックの方法
アルコールチェックは対面で行うのが基本です。安全運転管理者は、目視およびアルコール検知器を使用して以下を確認します。
・目視:運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子など
・アルコール検知器:呼気中のアルコール濃度の測定
アルコールが検出された場合、運転させず、代わりに他の業務を指示してください。
| アルコールチェックの対象者 | 業務で運転を始める人や運転を終えた全員が対象です。役員や従業員を問わず、業務のための運転であれば、社有車、私有車、リース車など全ての自動車の運転者が対象となります。ただし、通勤や私用のための運転、業務でない日に運転しない人は対象外です。 |
| 対面での確認が難しい場合 | 直行直帰などで対面確認が困難な場合は、代替方法で確認します。例えば、携帯電話やカメラ、モニターを使用して、安全運転管理者が運転者の顔色や応答の声の調子を確認する方法です。また、運転者に携帯型アルコール検知器を持たせ、その結果を報告させることもできます。安全運転管理者が不在の場合は、補助者や副安全運転管理者がチェックを行うことも可能です。 |
| 確認のタイミング | 運転の直前や直後でなくても、始業時や終業時のチェックでも問題ありません。また、1日に複数回運転する場合は、その都度のチェックは必要ありません。 |
4.アルコールチェックの記録保持
安全運転管理者によって行われたアルコールチェックの記録は、1年間保持することが義務付けられています。記録の保管方法については特に指定されていないため、紙やデジタル形式など、各企業に適した方法で保管できます。記録に含めるべき内容は以下の通りです:
① 確認者の名前
② 運転者の名前
③ 運転者が業務で使用する自動車のナンバーまたはそれを識別できる記号や番号
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法(対面でない場合は具体的な方法を記載)
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他必要とされる事項
5.アルコールチェックの違反に対する罰則
安全運転管理者がアルコールチェックなどの業務を怠った場合の直接的な罰則はありませんが、安全な運転の確保が行われていないと判断されると、都道府県公安委員会から安全運転管理者の解任命令が出されることがあります。また、アルコールチェックの有無に関わらず、実際に飲酒運転を行った役員や従業員がいた場合、運転者だけでなく、車両提供者として企業にも罰則が科される可能性があります。
就業規則等による従業員への周知
アルコールチェックを効果的に行うためには、従業員に十分に周知することが不可欠です。そのため、就業規則や社内のルールを見直し、アルコールチェックに関する規定を設けることが大切です。例えば、規定には以下のような内容を含めることが考えられます。
(アルコールチェックの実施方法)
・飲酒の有無を確認する方法
・チェックの記録や保存方法
・飲酒が確認された際の対処法など
(服務規律)
・飲酒運転やそれを助ける行為の禁止
・勤務中の飲酒に関するルール
・勤務時間外の飲酒について、翌日の勤務時に影響がないよう注意するなど
(懲戒処分)
・飲酒運転やその助長行為をした場合
・アルコールチェックを拒否した場合など
加えて、安全運転管理者の選任、社用車の点検・整備、事故時の対応、私用車の業務利用、法令遵守などを含む車両管理規程の作成もおすすめします。
従業員教育
従業員にアルコールチェックの大切さや飲酒運転防止のための取り組みを理解してもらうために、社内研修や自動車学校などで実施される企業向けの研修プログラムを利用するのが良いでしょう。また、警察庁や都道府県警察が作成する飲酒運転防止のリーフレットを職場に掲示するなど、啓発ツールを活用することも効果的です。
アルコールチェックは単に法令を遵守するためだけではなく、運転する従業員や他者の命を守るための重要な取り組みです。役員や従業員が飲酒運転を起こした場合、企業の信頼も失われる恐れがあります。そのため、アルコールチェックの徹底と従業員教育を十分に行うことが非常に重要です。
それでも労働問題にお困りなら

代表の引地です。
あなたのお悩みを解決します!
弊社の社会保険労務士事務所は、多くの企業様の労働問題を解決へと導いてまいりました。
その実績は、確かな知識と経験に基づいております。
なぜ労働問題の解決が可能かというと、専門家が常に最新の法律や判例を基に、適切な助言を行なっているからです。
サービス内容としては、労務相談を始め、給与計算、手続代行、就業規則の作成など幅広く対応しております。問題を抱えている企業様、安心してご相談ください。詳しいサービス内容については、こちらのリンクからご確認いただけます。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
8:30~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。